先日から食事で親と違うものが提供されるのが嫌なのか、提供されたものじゃないものがいいのか、自己主張がみられるようになってきました。
食事の自己主張をどこまで受け入れるかについて考えていきます。
我が家は共働きのため保育園に預けていますので、ご迷惑にならないよう、わがままっこにならないように注意しなきゃなぁと意識はしていますが…
自己主張の芽生え・発達の背景
・共同注意・ジェスチャーの発達
9か月〜1歳3か月で「指差し」「相手と注意を共有する」力が伸び、1歳頃の指差しや身振りはその後の言語発達を予測するようです。意思表示が洗練される一方、伝わらない苛立ちが増えるようです。
・自己の芽生え・自己認識
鏡の前の自分を「自分」と認識できる力は、おおよそ1歳3か月〜2歳くらいで多くの子に現れるようです。事故が立ち上がると「自分で!」「それじゃない!」が増えるようです。
・言語表出の未熟さとフラストレーション
1歳〜3歳では、表出言語が未熟だと癇癪(泣き・怒り)が強くなりやすいことが示唆れています。(Manning BL, et al. 2019)
ただ一般的に癇癪は普通におこる現象とされていて、1歳〜1歳半頃始まり、2〜3歳でピーク、4〜5歳で減少するようです。1歳半〜2歳で約8〜9割が経験するようです。
食行動に関する科学的知見
・レスポンシブ・フィーディング(応答的な食事関与)が基本
国際ガイドライン(WHO)によると、子供の空腹・満腹サインを尊重し、無理強いしない、時間と環境を整えることが推奨されています。ようは、家族と一緒だとか、静かな環境だとか、ゆっくり声掛けするだとか…を指すようです。
・繰り返し暴露で受け入れが増える
同じ食品を何度も少量で経験させることによって、好みと摂取量が増えるようです。ご褒美を与えるよりも単純な反復経験の方が有効というデータもあります。(Wardle J, et al. 2003. Hausner H, et al. 2012)
・食べ渋りもあるようですが、反復的な暴露や親が美味しそうに食べることも改善に効果的なようです。
・親の関わり方・スタイルが食行動に影響を及ぼす可能性
説明と温かさを伴う一貫した関わりが望ましい食行動に関連し、厳格・許容的すぎは偏食や食事ストレスと関連するようです。
・1食程度スキップしても大丈夫
空腹を経験させることも大事。だが、保育園に行ってから機嫌が悪くなることが予測される場合の予防的な対処として、バナナ・牛乳・ヨーグルトなどの軽食対応は許容するとか。おかしはNG→泣くとおやつがもらえると認識する学習を防ぐため。
対応について
知識を実践に落とし込むのは、なかなか、こども相手だと特に難しさが増しますね。
親の関わり方はどうやら大事そうです。環境設定・声掛け・時間タイミング、それから子供に選択させることも必要そうな。
癇癪を起こすのは一般的だと理解したうえで、余裕をもって対応しなければならないと感じました。
特に言語表出が難しい時期は、そういった苛立ちが増してきて、食事をとらないと悪循環に陥ってしまうと収拾がつかなくなってしまうと。
まぁいい日もあれば、うまく行かない日もあるので、1日だけじゃなく、中長期的に考えなければいけない、短期目線で怒鳴りつけることは決してないようにしたいなと思いました。
また、画像やアイキャッチなどは時間がとれたら、更新したいと思います。
ここまで、お読みくださり、ありがとうございました。
また子育てに関することメインに、+自分の生活についても発信できればと思います。
よろしくお願いいたします。
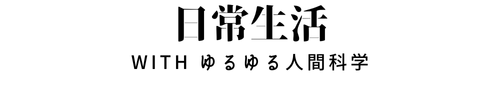


コメント